私は2次試験のリスクヘッジとして1年目の2次試験後から2年目への挑戦と養成課程の検討してました。
結果的には養成課程に進むことになりましたが、現時点では早めに検討しておいてよかったなと思ってます。
2次試験再挑戦
中小企業診断士試験の1次試験を突破した後は2次試験に進めます。
2次試験は2回受けることができるので私は1年目はそのまま何も考えずに試験に挑みました。
結果不合格となり、自動的に2年目再挑戦を目指すこととなりました。中小企業診断士はテストの日から合格発表まで約2か月強あるので、その間はもやもやした気持ちで過ごすことになります。
この期間は自分のスキルアップのためと再テストを目論んで簿記の勉強をしてました。
年明け1月に不合格ということがわかり、そこから本格的に再挑戦に向けてどうしていこうかなと考え始めました。
養成課程の説明会
2年目への再挑戦をするのと並行して、養成課程に関しても準備進めておこうと思い説明会に参加し始めました。
1次試験が終わってから開催されることが多いと思いますが、私の場合は春頃から興味のある学校をリストアップしていつ行うのかチェックし始めました。
チャンスを逃すとわからなくなるので、自分から情報はとるようにしてました。
そう思って取り組んだ結果、各機関の特色をつかめたことと、副次的に今国から求められている診断士像を知ることができたのは大きかったと思います。
勉強しているだけなら触れることができない情報を説明会で知ることができて、自分の将来像をイメージできるようになりました。
これは養成課程の先生方が実際の診断士として活動しているからの利点だと思います。
どういう診断士が求められているのかわからない人は、実際に養成課程を受験しないにしても参加するのは良い経験になるかもしれません。
2次試験から養成課程の受験まで
2次試験が終わってから本格的に受験に向けて準備し始めました。
説明会も改めてここから本格的に参加し始め、どういうスケジュールで資格取得まで進めるのか見直しました。
私は働きながらを選択したので必然的に平日夜と土日で取れる機関が選択肢になりました。
いくつかピックアップした後はオンラインの説明会に参加し、パンフレットを取り寄せ、募集要項に沿って準備を始めました。
出願期間は11月中が多かったため、一息つく暇もなく願書の作成に取り掛かりました。
大枠としてはなぜ診断士を目指すのか、どうしてここの養成課程を志望するのかという点がければつぶしが効くと思います。
実際書類関係で落ちることはなく、すべて最終選考まで残れたのでよっぽどじゃない限り面接にはたどり着けると思います。
大学の成績証明書や卒業証明書が必要になってくるところもあるので、今一度手元に持っているのか確認しておくとバタバタしなくて済むと思います。
おわり

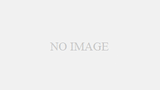
コメント